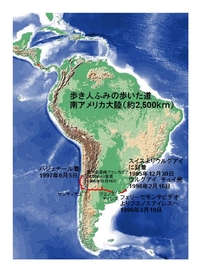2008年01月16日
3ヶ月前に思いついた地域再生モデルがスタート
新たな地域再生プロジェクト「ecoぴよ」ついに始動します!!
3ヶ月前に思いついた地域再生モデルのビジネスが、ついにスタートしました。
この地域再生モデルは、スポーツビジネスとecoビジネスを融合させたものです。
スポーツビジネスは、①興行収入(メディア放映なども含む) ②グッズ収入 ③広告収入(ユニフォームなどのロゴ使用権など) ➃寄付収入 ⑤その他の収入(他の事業からの支援) の5つに分類できます。
ところが、このビジネスモデルは、基本は①ありきのビジネスで、集客能力が高くなければ、②も③も➃もなりたたないものです。お客様を集めてナンボという商売です。
そうなると、<市場の大きなところがどうしても有利>になります。
対象となるスポーツ人口比率(観客になってくれる人の割合)が3㌫と仮定したとして、
人口100万人の都市なら、3万人の市場があります。
3万人が年間2試合足を運んだとして、1試合平均単価3000円とすれば
3万人×2回×3000円=1800万円 の興行収入が見込めます。
ところが、これが人口40万人都市だとすると一気に変わります。
同じ計算をすれば、母集団は1万2000人。
興行収入は、720万円。
人口の規模がそのまま、収入の差につながるわけです。
つまり、スポーツビジネスは大都市向きのビジネスといえます。
では、地方でスポーツビジネスをやりくりするためにはどうすればいいのかといえば、
***********
<企業依存型>
絶対的に強いスポンサーをつけることで、赤字運営でも可能にする。
*********************************
これが圧倒的な主流です。99㌫このスタイルといっても過言ではありません。
地域運営型を掲げているサッカーでさえも、この格差は例外ではありません。
トップチームをみれば一目瞭然です。おおよそ、母体となる企業があります。
浦和ならば三菱が、鹿島なら住友がというふうにです。
また、J2以下のチームが、ほとんど中規模都市より小さいのも戦力格差を
生み出している事例で、資金力の差がやはり選手の格差ともなっている
わけです。
となると、中規模以下の都市でスポーツビジネスを行うためには、
圧倒的なリピーターを集め、一人あたりの単価を上げるのが必要となります。
*最低でも地方の中核都市でないと、難しいというロジックが生まれます。
*成功したのがアルビレックス新潟でしょう。
→新潟は中規模よりも大きく、また交通面でも便利な地域(東京にも意外と近い)
などの諸要素もあり、安易にいえませんが。。
しかし、企業依存型のスポーツビジネスは、その多くの命運を企業の業績に
ゆだねられています。また、経済合理性でいえば、もっともお得なのは
固定費の少なく、宣伝効果も見越せるマラソンのような優等生スポーツ
(マラソンは少人数でもいいし、ホームグランドの整備もいらない。けれども
マラソンを走っている2時間は、トップグループにいればずっと広告できる
最良の広告媒体でもある。)
などに、どうしても目がいってしまいます。
また、強くなればなるほど人件費や交通移動費などの固定費が大きくなり、
非常にコストが高くつきます。
ですので、
*********
企業依存せずにスポーツビジネスを行うのがいかに難しいか。
****************************
これは、地方でがんばっているスポーツ団体すべての頭を悩ませている
モンダイだと思います。
これをどのようにしてクリアにしていくのか。
そこで考えたのが、
多くの支援企業様を集める寄付モデルを作り上げ、企業依存型モデルを
修正して行うというものです。
いまこの寄付モデルを実際に運用し始めたのが
女子バレーボールチーム
「四国Eigthy8クイーンバレーボール」です。
http://www.eighty8.jp/
寄付モデルはこういうものです。
***********
バレーチーム;ロゴを貸すことで寄付をいただく。
中小企業;新規事業を行う。
新規事業の売り上げの1パーセントをチームに寄付する。
******************************
というシンプルなものです。
まず、この寄付モデルは売り上げの1パーセントということで
企業側は安価にロゴを借りることができ、コスト負担も非常に
少ないモデルです。
これまで大企業依存型のモデルでは、企業チームの側面が強く、
企業業績に大きく左右されるのが最大のリスクでした。
今回の寄付モデルは、社会貢献型のビジネスを新規事業として積極的に
行っていこうとする中小企業に門戸を広げ、多くの地域の支えを広げて
いこうというモデルです。
今回進めているのは、
現在バレーチームを支援している100社近い企業の資源ゴミを集め、
その売り上げの1パーセントを寄付するというモデルにしました。
多くの会社がその処理に困っている資源ゴミが、チーム運営の資金となる
という仕組みです。
支援企業もコストカットになり、三方両得のモデルです。
一番最初のモデルケースとして有限会社中讃ライフサービス様が資源ゴミ
回収を行い、資源ゴミを出す側にJA様、コカコーラボトラーズ様との提携が
決まりました。
このモデルケースが多くの中小企業様にも受け入れられ、
年商1000万円程度の売り上げが見込める新規事業を100ケース
生み出すことができればと考えています。
もしこれが現実のものとなれば、
四国に年商1000万円×100ケース=10億円 の新規事業が生まれ、
そして寄付金1000万円がチームの支援金となる。
このケースが呼び水となり、多くの支援企業がさらにスポンサーとして
多くの資源貢献をしていただくことで、多くの効果が生まれるのではと
考えています。
ぜひ、支援企業としてお手伝いいただける企業様、個人事業主様が
いらっしゃればご一報ください。
新たな社会貢献型ビジネスの創出の担い手として応援していただくことを
願っています。
3ヶ月前に思いついた地域再生モデルのビジネスが、ついにスタートしました。
この地域再生モデルは、スポーツビジネスとecoビジネスを融合させたものです。
スポーツビジネスは、①興行収入(メディア放映なども含む) ②グッズ収入 ③広告収入(ユニフォームなどのロゴ使用権など) ➃寄付収入 ⑤その他の収入(他の事業からの支援) の5つに分類できます。
ところが、このビジネスモデルは、基本は①ありきのビジネスで、集客能力が高くなければ、②も③も➃もなりたたないものです。お客様を集めてナンボという商売です。
そうなると、<市場の大きなところがどうしても有利>になります。
対象となるスポーツ人口比率(観客になってくれる人の割合)が3㌫と仮定したとして、
人口100万人の都市なら、3万人の市場があります。
3万人が年間2試合足を運んだとして、1試合平均単価3000円とすれば
3万人×2回×3000円=1800万円 の興行収入が見込めます。
ところが、これが人口40万人都市だとすると一気に変わります。
同じ計算をすれば、母集団は1万2000人。
興行収入は、720万円。
人口の規模がそのまま、収入の差につながるわけです。
つまり、スポーツビジネスは大都市向きのビジネスといえます。
では、地方でスポーツビジネスをやりくりするためにはどうすればいいのかといえば、
***********
<企業依存型>
絶対的に強いスポンサーをつけることで、赤字運営でも可能にする。
*********************************
これが圧倒的な主流です。99㌫このスタイルといっても過言ではありません。
地域運営型を掲げているサッカーでさえも、この格差は例外ではありません。
トップチームをみれば一目瞭然です。おおよそ、母体となる企業があります。
浦和ならば三菱が、鹿島なら住友がというふうにです。
また、J2以下のチームが、ほとんど中規模都市より小さいのも戦力格差を
生み出している事例で、資金力の差がやはり選手の格差ともなっている
わけです。
となると、中規模以下の都市でスポーツビジネスを行うためには、
圧倒的なリピーターを集め、一人あたりの単価を上げるのが必要となります。
*最低でも地方の中核都市でないと、難しいというロジックが生まれます。
*成功したのがアルビレックス新潟でしょう。
→新潟は中規模よりも大きく、また交通面でも便利な地域(東京にも意外と近い)
などの諸要素もあり、安易にいえませんが。。
しかし、企業依存型のスポーツビジネスは、その多くの命運を企業の業績に
ゆだねられています。また、経済合理性でいえば、もっともお得なのは
固定費の少なく、宣伝効果も見越せるマラソンのような優等生スポーツ
(マラソンは少人数でもいいし、ホームグランドの整備もいらない。けれども
マラソンを走っている2時間は、トップグループにいればずっと広告できる
最良の広告媒体でもある。)
などに、どうしても目がいってしまいます。
また、強くなればなるほど人件費や交通移動費などの固定費が大きくなり、
非常にコストが高くつきます。
ですので、
*********
企業依存せずにスポーツビジネスを行うのがいかに難しいか。
****************************
これは、地方でがんばっているスポーツ団体すべての頭を悩ませている
モンダイだと思います。
これをどのようにしてクリアにしていくのか。
そこで考えたのが、
多くの支援企業様を集める寄付モデルを作り上げ、企業依存型モデルを
修正して行うというものです。
いまこの寄付モデルを実際に運用し始めたのが
女子バレーボールチーム
「四国Eigthy8クイーンバレーボール」です。
http://www.eighty8.jp/
寄付モデルはこういうものです。
***********
バレーチーム;ロゴを貸すことで寄付をいただく。
中小企業;新規事業を行う。
新規事業の売り上げの1パーセントをチームに寄付する。
******************************
というシンプルなものです。
まず、この寄付モデルは売り上げの1パーセントということで
企業側は安価にロゴを借りることができ、コスト負担も非常に
少ないモデルです。
これまで大企業依存型のモデルでは、企業チームの側面が強く、
企業業績に大きく左右されるのが最大のリスクでした。
今回の寄付モデルは、社会貢献型のビジネスを新規事業として積極的に
行っていこうとする中小企業に門戸を広げ、多くの地域の支えを広げて
いこうというモデルです。
今回進めているのは、
現在バレーチームを支援している100社近い企業の資源ゴミを集め、
その売り上げの1パーセントを寄付するというモデルにしました。
多くの会社がその処理に困っている資源ゴミが、チーム運営の資金となる
という仕組みです。
支援企業もコストカットになり、三方両得のモデルです。
一番最初のモデルケースとして有限会社中讃ライフサービス様が資源ゴミ
回収を行い、資源ゴミを出す側にJA様、コカコーラボトラーズ様との提携が
決まりました。
このモデルケースが多くの中小企業様にも受け入れられ、
年商1000万円程度の売り上げが見込める新規事業を100ケース
生み出すことができればと考えています。
もしこれが現実のものとなれば、
四国に年商1000万円×100ケース=10億円 の新規事業が生まれ、
そして寄付金1000万円がチームの支援金となる。
このケースが呼び水となり、多くの支援企業がさらにスポンサーとして
多くの資源貢献をしていただくことで、多くの効果が生まれるのではと
考えています。
ぜひ、支援企業としてお手伝いいただける企業様、個人事業主様が
いらっしゃればご一報ください。
新たな社会貢献型ビジネスの創出の担い手として応援していただくことを
願っています。
Posted by おおにぴ at 11:52│Comments(0)
│ビジネスコラム
※会員のみコメントを受け付けております、ログインが必要です。